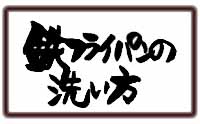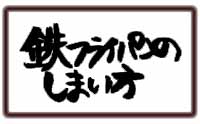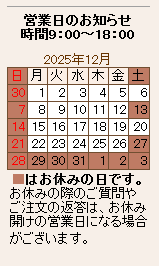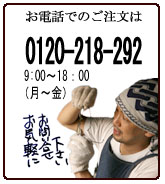鉄フライパンでピーマンを上手に炒める
ピーマンは、炒め方ひとつで見た目も味も、そして栄養までもが大きく変化する、ちょっと不思議でとても面白い野菜です。
特に「鉄フライパン」を使って炒めることで、その変化をより深く味わうことができ、しかも栄養価の点でも嬉しい効果があったりします.
今回は、鉄フライパンだからこそ引き出せるピーマンの魅力と、科学的な根拠を交えながらご紹介します。

ピーマンは炒め方で「栄養の質」が変わる野菜
ピーマンといえば、ビタミンCが豊富なことで知られています。
一般的にビタミンCは熱に弱い栄養素ですが、ピーマンの場合は細胞壁がしっかりしていて加熱しても比較的壊れにくい性質があります。
実際、加熱しても60〜70%ほどのビタミンCが残るとする報告もあり(※1)、炒め物でもその恩恵を十分に受けられます。
でも、これは「火加減」によって大きく左右されます。
ピーマンの栄養素を守るには、急激な高温を避けることと過度な加熱をしないこと
が大切です。
鉄フライパンで板厚が厚いタイプは熱伝導はゆっくりですが蓄熱性が非常に高い調理器具で、つまり一度温まると安定した温度で食材を包み込むように加熱できます。
この”じんわり火が入る”という特性が、ピーマンのビタミンCなどの栄養素を守りつつ美味しく炒めてくれ最適です。
鉄フライパンで「鉄分」が補える?栄養面の隠れた効果
さらに、「鉄フライパンを使うことで鉄分が微量に料理へ溶出する」という点です。
この現象は特に酸性の食材や水分を含む料理において顕著ともいわれています。
ピーマン自体には鉄分が含まれていますが、非常に微量です。
しかし、鉄フライパンを使って炒めることで、その鉄分を補完的に摂取できる可能性があります。
色の変化も科学的に解明されている
ピーマンの「緑色」は、焼き方によって変わりますよね?
これはクロロフィル(葉緑素)という色素が熱や酸によりフェオフィチンという褐色成分に変わってしまうことが原因です。
美しい緑色を保つには、
• 強火を避けて中火で調理
• 調味料(特に酸性)を最後に加える
• 過加熱しない(1〜2分で火から外す)
といったコツが必要です。
これを活かすにはフライパンを振ったり、蓋をしないなどテクニックを活かせます。
苦味の正体とその変化
ピーマンの苦味のもとは「クエルシトリン」というフラボノイド系の成分です。
この成分は加熱によって分解されることが分かっており、炒めることで苦味がやわらぐのはこのためです。
さらに、焼き目をつけることで香ばしさが加わり、苦味がほとんど気にならなくなります。
実験的にも、「皮側から焼いたピーマンの方が、果肉側から焼いたものより苦味を感じにくい」とする感覚評価の結果があります。
また、ピーマンは油との相性が良く、油が苦味成分をマイルドにする効果もあります。
鉄フライパンは油馴染みが良いため、この点でもピーマン調理に向いています。
ピーマンは「生でもいける」からこそ楽しい
ピーマンの魅力のひとつは、「生でも食べられる」ことです。
つまり、火入れの幅が非常に広いということ。
• シャキシャキ感を活かしたいなら、強火で1分以内の炒め
• 甘味を引き出したいなら、弱火でじっくり炒める
• 焼き目と香りを重視するなら、皮側を下にして1〜2分焼く
火を入れすぎれば栄養も色も失われ、苦味も戻ってきます。
逆に、火をうまくコントロールすれば、苦味を飛ばし、緑を残し、栄養も逃がさない。
まさに「技の見せどころ」になる食材です。
ピーマンは、調理の工夫次第でいくつもの顔を見せる魅力的な野菜。
それが鉄フライパンなら
• 栄養素(ビタミンC・鉄分)を逃がさず
• 美しい緑を保ち
• 苦味をマイルドに仕上げる
という調理も実現できます。
しかも、鉄分補給という健康面のメリットまでプラスされるのです。
ピーマンが苦手な方も、ぜひ一度この方法で調理してみてください。
参考文献
※1:五明紀春『食品成分表2024』女子栄養大学出版部
※2:厚生労働省「食事摂取基準(2020年版)」/調理器具からの鉄分溶出に関する報告
※3:佐藤ら(2012)「ピーマンの苦味成分と加熱処理による官能評価」調理科学研究会誌