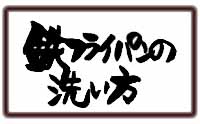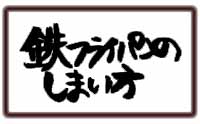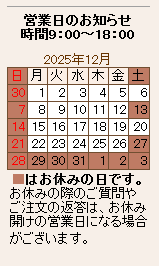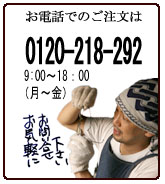鉄フライパンを使うと鉄分が摂れるって本当?
鉄フライパンを使うと鉄分が摂れるって本当?その仕組みをわかりやすく解説します。
「鉄フライパンを使うと鉄分が摂れる」って、どこかで聞いたことありませんか?
でも「鉄って固くて形があるし、どうやって体に取り込まれるんだろう?」と、素朴に疑問に思ったこと、きっとあると思います。
実際に手に取ると、鉄フライパンは重くて硬い金属の塊です。
そんな鉄が料理に溶け込んで、それが私たちの体に入るなんて、ちょっと不思議ですよね。
今回は、その疑問をできるだけやさしく解きほぐしながら、「どうして鉄フライパンを使うと鉄分が摂れるのか?」をわかりやすくご説明します。
鉄フライパン製造者としての視点から、科学的な根拠も交えつつ、日常の料理で活かせるポイントまでお伝えしていきます。
鉄フライパンからどうやって鉄が料理に移るの?
まず、鉄は非常に硬い金属です。だから、「そんな固いものが溶け出すの?」と思うのは当然のこと。
ですが、調理の過程で鉄フライパンの表面は水分や酸と接触し、化学反応がわずかに起こります。
硬い鉄でも溶けるの?そのメカニズムとは
どんなお料理でも鉄フライパンと触れて調理されるので、鉄分は移るのですが、特に、トマトやお酢、しょうゆ、味噌といった発酵食品や酸味のある食材や調味料を使うと、フライパンの表面から微量の鉄が料理に移るのです。
この反応は目に見えるものではなく、ごくわずかな量ですが、毎日の調理を通じて積み重なり、自然な鉄分補給に繋がっています。
科学的根拠:鉄フライパンで鉄分アップの実証データ
実際、国の研究機関の調査でも、鉄フライパンで調理した料理は、ステンレスやテフロン製の調理器具で作ったものと比べて、1.5倍から3倍も鉄分が多いというデータがあります。
つまり、鉄フライパンは効率的に鉄分を摂取できる調理器具であると言えます。
鉄はなぜ体に必要?鉄の役割と吸収のポイント
鉄は、赤血球のヘモグロビンという成分の材料です。
ヘモグロビンは血液中で酸素を体全体に運ぶ役割を担っています。だから鉄が不足すると、酸素の運搬がスムーズにいかず、疲れやすくなったり、立ちくらみやめまいなどの症状が出る「鉄欠乏性貧血」になることがあります。
よく言われるのが、女性や成長期の子ども、高齢者の方です。
と言うのは鉄不足になりやすいため、毎日の食事で意識的に鉄を補うことが大切と言われています。
ヘム鉄と非ヘム鉄の違いと吸収のポイント
食事から摂る鉄には「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」があります。ヘム鉄は肉や魚に多く、吸収率が高いのが特徴。
一方、鉄フライパンから摂れる鉄は「非ヘム鉄」と呼ばれ、こちらの吸収率はやや低めですが、ビタミンCや動物性たんぱく質と一緒に摂ると吸収が良くなります。
非ヘム鉄の吸収を助ける食材の組み合わせ
例えば、鉄フライパンでトマトやピーマンなどのビタミンCを含む野菜とお肉を炒めると、鉄の吸収を効果的に助けることができます。
だから、ただフライパンを使うだけでなく、食材の組み合わせも工夫するとさらに効果的です。
鉄フライパンの鉄臭さは大丈夫?使い方とお手入れのポイント
「鉄の臭いや味が気になる」という方もいらっしゃいますが、正しいお手入れをすればほとんど気になりません。
特に私たちでお知らせしている上手に使う方法2つ目、水またはお湯を流しながらこすり洗いをする(洗剤は使わない)や、使い終わったらフライパンの水気をしっかり拭き取り、できる方だけで結構ですけどその後薄く油を塗っておくと、フライパンが「育つ」と言われる状態になり、鉄臭さが抑えられます。
錆びや空焚きによる臭いの原因と対処法
ただし、錆びたり空焚きすると鉄臭さが出ることがあるので注意が必要です。
そうなると料理の味に影響することもあるため、毎日の手入れを大切にしてください
特に上手に使う方法は有効です
鉄フライパンは自然な鉄分補給の味方
また、鉄フライパンはサプリメントのように大量の鉄を一気に摂るのとは違い、日々の料理で少しずつ自然に鉄分を補う方法です。だから胃への負担も少なく、安心して長く使えます。
よくいただく質問で関連のあるものを少し書き出しましたのでよろしければご覧ください。
質問(FAQ)
Q1: 鉄フライパンから本当に鉄分は摂れる?
はい。ごく微量ですが、酸や水分と反応して鉄が料理に移ります。毎日使うことで自然な鉄分補給につながります。
Q2: 鉄の味や臭いは気になりませんか?
適切なお手入れをしていれば気になりません。むしろ食材の旨味が引き立つという声も多いです。
Q3: 鉄の吸収率はどうですか?
鉄フライパンからの鉄は非ヘム鉄ですが、ビタミンCや動物性たんぱく質と一緒に摂ると吸収がアップします。