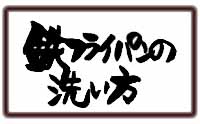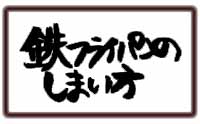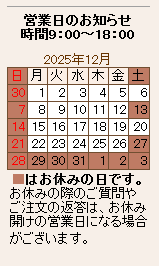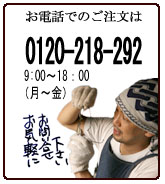鉄フライパンの“あえて言う”悪いところ──でも、それもまた魅力です
前回、鉄フライパンの“良いところ”をたっぷりお話ししました。
お肉がジューシーに焼けるとか、道具として育つ楽しさがあるとか、家族の思い出が刻まれるような存在だとか…。
鉄フライパンを使う楽しみ、きっと少しでも伝わったのではと思います。
でも今回は、あえて“悪いところ”もお伝えしたいと思います。
というのも、道具って「いいこと」だけを聞いて選んでしまうと、いざ使い始めて「思ってたのと違う…」となりがちなんですよね。
鉄フライパンにも、付き合っていく上で知っておきたい“クセ”や“弱点”がいくつかあります。
けれど、その「悪いところ」を知っていると、うまく付き合えたり、逆にそれを活かすこともできたりするんです。
今回は、そんな視点から、「鉄フライパンって、ここがちょっと難しいかも」「でもそれって、実はこういう意味があるよね」というお話をしていきます。

錆びる。やっぱりこれは“鉄の宿命”
鉄は、濡れたまま放置すると錆びます。
これはもうどうしようもない事実。洗ったあとは、できれば火にかけて乾かす。
慣れてしまえば当たり前のことなんですが、最初は「うっかりそのままにしてた…」なんてことも。
でも、実はこの“錆びやすさ”があるからこそ、鉄フライパンは「育つ」し、「手をかける道具」になるとも言えるんです。
ちょっと面倒ではあるけれど、その手間をかけることで、どんどん使いやすく、愛着のわく道具になっていく。
錆びることを知っているからこそ、自然と扱いが丁寧になります。
鉄の匂いがする?──食材や味付けによっては、においが気になることも
鉄フライパンで調理して、「なんだかちょっと鉄っぽい匂いがするかも…?」と感じたこと、ありませんか?
実はこれ、食材や調味料との相性によって起きる現象です。
特に酸味の強いもの(酢やトマトなど)や、長時間の煮込みをするときには、鉄分が溶け出して鉄っぽい風味や匂いが移ることがあります。
これは悪い面として語られがちですが、身体にとっては鉄分補給にもなり得るもの。
鉄鍋で煮た料理の鉄分が、実際に体に吸収されやすい「非ヘム鉄」に近い形で摂れるという研究もあります。
とはいえ、例えばジャム作りなどは他の鍋にする、という使い分けもおすすめです。
食材によっては、色がくすむ・黒ずむこともある
鉄フライパンを使っていると、調理後に食材の色が少しくすんでしまうことがあります。
例えばこれは特に、色の淡い野菜やきのこ、れんこんやエノキなどで感じることがあるかもしれません。
でも実はこれ、鉄分と食材に含まれる成分が反応して起きる「色の変化」なんです。
鉄と食材のタンニンや酸が反応して、色が変わる。
見た目はちょっと地味になってしまいますが、これもまた“鉄で調理している証拠”。
ちょっと面白いのは、この性質を逆に“活かしている”昔ながらの知恵があったりします
昔のおばあちゃんは知っていた──鉄の作用を「活かす」工夫たち
たとえば、ナスの漬物に釘を入れるという知恵。昔から「ナスの色がきれいに出る」と言われてきましたよね。
これは、鉄釘からごく微量に溶け出した鉄分がナスと反応して、鮮やかな紫色を保つから。
他にも、黒豆を煮るときに“くぎ”や“鉄玉”を入れるというのも有名です。
これは、黒豆の色素(アントシアニン)が鉄と反応して、より黒く、ツヤツヤに仕上がるため。
つまり、鉄の性質は時には「悪いところ」として現れるけれど、使い方次第では“調理の知恵”になるんですね。
鉄フライパンのちょっとした“クセ”も、昔の人たちはうまく使いこなしていたんです。
食べ終わってもそのまま──“入れっぱなし”が苦手なフライパン
お料理をしていると、ついやってしまいがちなのが「作った料理をそのままフライパンに残したままにしておく」ということ。
でも、これ、鉄フライパンにはあまり向いていません。
たとえば、後から食べる人用にフライパンにそのまま置いておく‥‥なんてやってしまうと、鉄と食材の成分が長く接触してしまい、
フライパンにダメージが出たり、サビの原因になったりすることもあります。
また、料理の風味に鉄っぽさが移ってしまうことも。
食材によっては、くすんだ色になったり、微妙な味の変化が起きることもあるので、調理が終わったらお皿へ移すのが鉄フライパンの“お作法”です。
便利だからこそやりがちな“入れっぱなし”ですが、鉄フライパンとは「調理したらすぐ盛る」が長持ちの秘訣ですね。
汁気の多い料理、実はちょっと苦手
鉄フライパンって、「焼く」には最高なんですが、「煮る」「蒸す」などの水分を使う調理は、あまり得意ではないんです。
長時間、汁気を残したまま放置してしまうと、サビの原因にもなりますし、前述した鉄臭や色の変化も起きやすくなります。
トマト炒めやカレーなんかをそのまま放置…なんてのは要注意。
煮込み料理は別の鍋、焼きや炒め物は鉄フライパン、といった使い分け”が必要になってきます。
最後に:欠点を知ることで、もっと上手に付き合える
鉄フライパンの“悪いところ”、いろいろ挙げてきました。
でも、こうして見るとそれって、単なる「短所」ではなく、鉄という素材そのものの性格だったり、工夫次第で活かせる特徴だったりするんです。
手間がかかるからこそ、愛着がわく。クセがあるからこそ、自分の暮らしに合った使い方が見つかる。
そういう意味では、「悪いところを知っておく」ことは、むしろ道具との付き合い方を深めてくれる、大切なステップです。
これから鉄フライパンを選ぼうとしている人、また、すでに使っていてちょっと扱いに悩んでいる人も、ぜひこの“クセ”や“個性”を知ったうえで、あなたのお料理や使い方に合うかどうか、考えてみてくださいね。
きっと、その先には、ちょっと素敵な付き合いが待っていると思います。